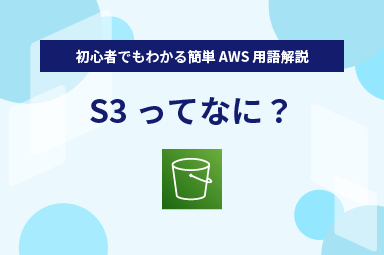ネットワークにおける基礎知識のひとつとして知られる「OSI参照モデル」は、さまざまなWebサービスを構築するにあたって知っておくべき重要な基礎知識になります。概要を知らなくてもWebサービスは実行できますが、より適切な形や効率化を求めるのであれば、OSI参照モデルについて知ることが改善のひとつのきっかけになるでしょう。
特にAWSを利用する場合には、OSI参照モデルについて知っておくことで、より最適なサービスの利用方法につながることがあります。
この記事ではOSI参照モデルの基礎知識について紹介します。
目次
AWSとは?
AWSは大手ネット通販を運営するAmazon.comが提供するクラウドコンピューティングサービスです。AWSを利用することで各社が提供するWebサービスにさまざまなメリットを付与することができ、これまで以上の環境をコンテンツにプラスできます。
特定の事業者だけではなく、幅広い業種がAWSの機能によってより良いIT環境を整えられるので、これから本格的なIT事業を展開していきたいと考えている企業に追い風になることでしょう。新規事業を始めたい、既存の事業を現在のインターネット体制に合わせて改善したいといった場合には、AWSの導入がおすすめです。
AWSは既に世界中の企業に利用されており、各社の事業を支える根源となっています。例えば世界中のあらゆるセキュリティ標準を満たした安全性、サービスの継続をサポートする耐障害性と高可用性、豊富なディベロッパーやユーザの情報を活かしたサービスの改善など、利用することで得られるメリットは多いです。
導入に至ってはサポートも受けられるため、自社に必要な具体的なサービスを確認しながら契約ができるでしょう。
AWSを利用することで、事業者は特に以下のような分野を充実させていくことができます。
- Webコンテンツのシステムと開発スピードの改善
- 重要データのバックアップを獲得
- 災害時も稼働する堅牢なシステムの構築
- ビッグデータの分析
- IoT、AIなど次世代サービスへの応用
これらのサービスを主体で運用している事業者はもちろん、別のサービスを軸として応用したい事業者もAWSから得られるメリットは大きくなります。事業者ごとのITインフラの確立は仕事をスムーズにするために不可欠なので、今からでもAWSを利用してみる価値はあるでしょう。
そんなAWSにはVPC(Virtual Private Cloud)と呼ばれる論理的に区切られた仮想ネットワークがあり、ネットワーク設定を細かくカスタマイズすることが可能です。VPCを活用するためにはネットワークの基礎知識が必要不可欠であるため、改めて基本的な知識を確保しておくことをおすすめします。
ほかにもネットワークの基礎を知っておくことで運用が楽になる可能性があるサービスがAWSにはあるため、この機会にOSI参照モデルについて学習しておきましょう。
OSI参照モデルとは?初心者にもわかりやすく解説
OSI参照モデルとは、コンピューターをはじめとした通信機器の機能を定義する国際標準化機構(ISO)によって決められた標準モデルです。OSI参照モデルを提供することでネットワークの仕組みを簡単に理解できるようにし、世界中で通信規格を共通のものにしようとしたという経緯が背景にあります。
さまざまな方法で通信が可能なネットワークに統一性を持たせることが目的でしたが、結果的にOSI参照モデルは使われることなく、今ではTCP/IPと呼ばれる基本ルールがネットワークの構築に役立っています。
そのためOSI参照モデルを知らない人も多く、そもそもの知識として不要なのではという意見もあります。
しかしOSI参照モデルを知ることはネットワークの基本を理解することにつながり、仕組みをスマートに学ぶことができるのです。
OSI参照モデルを理解することで、直接的に事業の進行をスピードアップしたり、より良い仕事環境をすぐに構築できるわけではありませんが、改善するためのきっかけになるかもしれません。OSI参照モデルはパッとみてわかりやすいような階層表記となっているので、ネットワークの初心者でも学びやすいのがポイントとなっています。
OSI参照モデルの階層
OSI参照モデルはネットワークが機能として所有すべきポイントを、7つの階層に分割しているのが特徴。この表を見ることで、ネットワークにどういった機能が必要なのか、どんな形で構築すべきなのかが把握しやすくなります。
| OSI参照モデルの階層 | 名称 |
| 第7層(レイヤ7) | アプリケーション層 |
| 第6層(レイヤ6) | プレゼンテーション層 |
| 第5層(レイヤ5) | セッション層 |
| 第4層(レイヤ4) | トランスポート層 |
| 第3層(レイヤ3) | ネットワーク層 |
| 第2層(レイヤ2) | データリンク層 |
| 第1層(レイヤ1) | 物理層 |
アプリケーション層
人間の行動に最も近い位置にあるのが、このレイヤ7のアプリケーション層です。Webプラウザに入れた情報から検索結果を表示したり、メールアドレスに合わせて送信したりといった、アプリケーションレベルでの処理機能を持つのが特徴です。
人間の求める結果をネットワークで処理できるように変換することが、第7層の役割となります。
プレゼンテーション層
文字のコードや圧縮形式などをチェックし、データを共通の形に変換するのがプレゼンテーション層です。例えば文字化けや画像の表示ミスが起こらないように処理するのが、共通の形に変換するというプレゼンテーション層のひとつの仕事となります。
異なるコンピューターでも同じ内容を表示できるようにサポートし、相互の意思疎通をさせることが役割です。
セッション層
通信における開始と終了までの手順を決めるのが、第5層のセッション層が担う役割です。システムを利用するアプリケーション間にセッションを確立し、論理的な接続をサポートします。
トランスポート層
通信における信頼性を確保するのが、第4層のトランスポート層です。さまざまな制御を行って通信データに情報を付加し、通信を信頼できる形にします。
ネットワーク層
通信相手が異なるネットワーク間にあってもデータのやり取りを可能とするのが、ネットワーク層の役割です。論理アドレスと呼ばれるIPアドレスを元にネットワークを識別し、転送に必要な情報を付け加えて定義します。
データリンク層
ネットワーク内にある通信相手のコンピューターを判断し、データのやり取りをサポートするのがデータリンク層の仕事です。データリンク層では物理アドレスのMACアドレスが識別に使われ、データの送信先を特定しています。
物理層
データを通信回線に送るのに必要な物理的な仕様を規定するのが、第1層の物理層です。コネクタの形状、ケーブルの種類、通信速度などの物理的な要素を決めることで、さまざまな機種同士でデータのやり取りが可能となります。
これらの階層を基準にして、順に処理された情報をヘッダとして階層にカプセル化することで、最終的には電気信号となって送信されていきます。
そして受け手側では逆に送信される過程で処理されたデータを取り除き、元々のデータに変える非カプセル化を行うのです。
OSI参照モデルではこの流れを基本としてネットワークが作られていると定義しているので、全体像を把握することでネットの基本的な構造を理解できるでしょう。
まとめ
OSI参照モデルを把握することで、ネットワークの内容は非常にわかりやすくなります。例えば、AWSのELB(ロードバランサ)がどの層に対応しているかなどを理解しやすくなり、よりよりサービスの選択をすることが可能になることでしょう。
この機会に通信の流れや階層の役割を把握してみてはいかがでしょうか。